医療費控除はいくらから申請できる?

「病院に行く機会が多かったけど、医療費控除っていくらから申請できるの?」「確定申告で医療費控除を申請したいけど、やり方がわからない…」このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
医療費控除は年間10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告で所得税の還付を受けられる制度です。しかし、単に10万円を超えればよいというわけではなく、所得に応じた基準があります。
この記事では、医療費控除の基本的な仕組みから実際の申請方法、見落としがちなポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。正しい知識を身につけて、支払った医療費を無駄にしないようにしましょう。
医療費控除の基本:いくらから対象になるのか

医療費控除とは?わかりやすく解説
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税を軽減できる制度です。この制度を利用することで、確定申告により税金の還付を受けることができます。
医療費控除の対象となるのは、本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族の医療費も含まれます。つまり、家族全員分の医療費をまとめて申請することが可能です。
10万円のボーダーライン(所得との関係も説明)
医療費控除を受けるための基準は「年間医療費が10万円を超える」または「総所得金額の5%を超える」のいずれか低い方となります。
医療費控除の基準額
- 総所得金額が200万円以上の場合:10万円
- 総所得金額が200万円未満の場合:総所得金額の5%
例えば、年収150万円の方であれば、医療費が7万5千円を超えれば医療費控除の対象となります。一方、年収400万円の方は10万円を超えなければ対象となりません。
対象となる医療費・対象外の医療費
医療費控除の対象となる主な医療費は以下の通りです:
- 病院や診療所での診療費・治療費
- 医師の処方による薬代
- 入院時の部屋代・食事代
- 通院のための交通費(公共交通機関)
- 治療のためのマッサージ・鍼灸費用
一方、対象外となるのは:
- 美容整形や審美歯科などの美容目的の治療
- 健康診断や人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合)
- 予防接種の費用
- マイカー通院のガソリン代・駐車場代
医療費控除で実際にいくら戻る?計算方法を解説
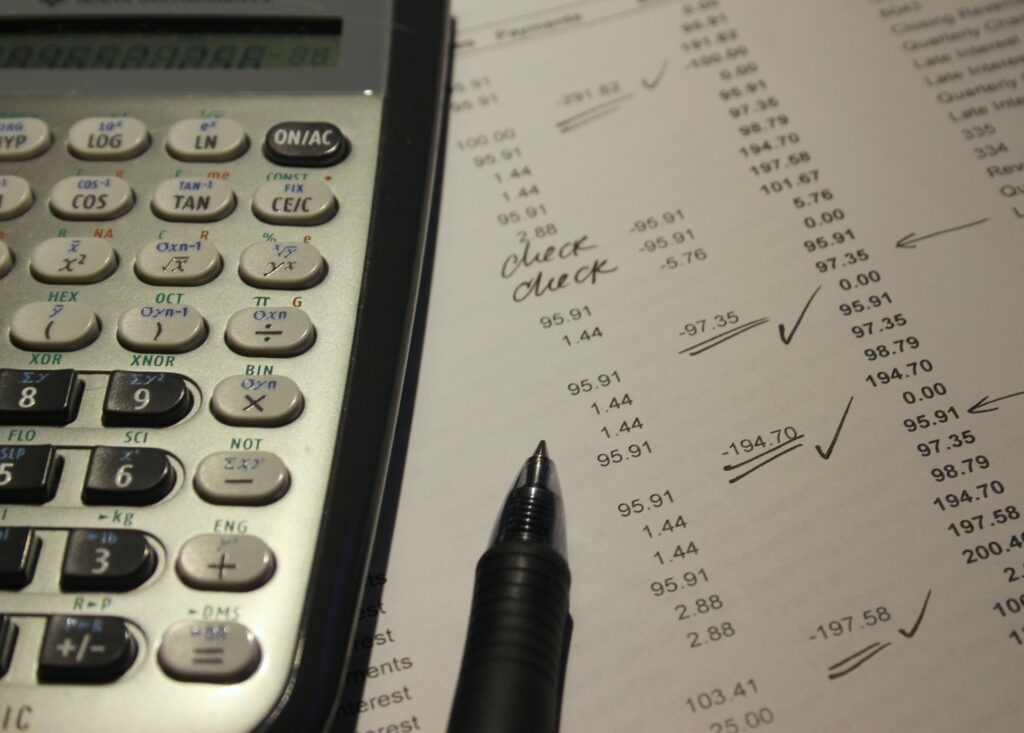
還付金の計算式をわかりやすく
医療費控除による還付金の計算は、以下の手順で行います:
還付金の計算手順
①医療費控除額 = 支払った医療費 - 基準額(10万円または所得の5%)
②還付金 = 医療費控除額 × 所得税率
重要なのは、支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではないということです。あくまで所得税の計算において控除される金額であり、実際の還付金はその方の税率によって決まります。
年収別シミュレーション例
具体的な例で計算してみましょう:
ケース1:年収400万円、医療費20万円の場合
- 医療費控除額:20万円 - 10万円 = 10万円
- 所得税率:10%
- 還付金:10万円 × 10% = 1万円
ケース2:年収600万円、医療費30万円の場合
- 医療費控除額:30万円 - 10万円 = 20万円
- 所得税率:20%
- 還付金:20万円 × 20% = 4万円
控除額と還付金の違い
多くの方が混同しがちなのが「控除額」と「還付金」の違いです。控除額は所得から差し引かれる金額であり、還付金は実際に戻ってくる税金です。
例えば、医療費控除額が10万円でも、還付金が10万円になるわけではありません。その方の所得税率によって実際の還付額が決まるため、高所得者ほど還付金も多くなる仕組みです。
医療費の集計方法と申請のコツ

領収書の整理・保管方法
医療費控除を申請するには、領収書の整理と保管が重要です。効率的な管理方法をご紹介します:
- 月ごとにクリアファイルや封筒に分けて保管する
- 家族ごとに色分けして整理する
- 医療機関名、受診者名、金額を一覧表に記録する
- 薬局のレシートも必ず保管する
領収書は確定申告の提出時には添付不要ですが、5年間の保管義務があります。税務署から問い合わせがあった際に提示できるよう、しっかりと保管しておきましょう。
医療費控除の明細書の書き方
確定申告では「医療費控除の明細書」の作成が必要です。この明細書には以下の項目を記入します:
- 医療を受けた人の氏名
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分(診療・治療、医薬品購入など)
- 支払った医療費の金額
- 生命保険などで補填された金額
明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。手書きでも作成可能ですが、e-Taxを利用すれば自動計算されるため、入力ミスを防げます。
スマホ・e-Taxでの申請手順
現在はスマホからでも簡単に確定申告ができます。e-Taxを利用した申請手順は以下の通りです:
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 「スマートフォンで申告書を作成する」を選択
- マイナンバーカードまたはID・パスワード方式でログイン
- 医療費控除の項目を選択し、明細を入力
- 計算結果を確認して送信
スマホでの申請なら、24時間いつでも申請可能で、税務署に行く必要もありません。確定申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。
よくある間違いと注意点
医療費控除でよくある間違いを事前に把握しておきましょう:
- 保険金の控除忘れ:生命保険や高額療養費で受け取った金額は医療費から差し引く必要があります
- 対象外費用の計上:健康食品や美容目的の治療費を含めてしまうケース
- 交通費の過大計上:マイカー通院の費用は対象外です
- 年をまたいだ計算:医療費は支払った年で計算するため、未払い分は翌年扱いになります
こんな場合も医療費控除の対象!見落としがちなケース

通院にかかる交通費
公共交通機関を利用した通院費用は医療費控除の対象です。電車代、バス代、タクシー代(緊急時や公共交通機関が使えない場合)も含まれます。ただし、マイカー通院のガソリン代や駐車場代は対象外です。
薬局で購入した市販薬
医師の処方薬だけでなく、薬局で購入した風邪薬や胃腸薬なども対象です。ただし、セルフメディケーション税制との併用はできないため、どちらが有利か比較して選択しましょう。
出産・不妊治療の費用
妊娠・出産に関わる費用の多くが医療費控除の対象となります:
- 妊婦健診の費用
- 分娩・入院費用
- 不妊治療費(体外受精など)
- 妊娠中の通院交通費
家族分もまとめて申請可能
生計を一にする家族の医療費は、最も所得の高い人がまとめて申請すると節税効果が高くなります。共働き夫婦の場合、所得税率の高い方が申請することで、より多くの還付を受けられます。
まとめ:医療費控除を賢く活用しよう

医療費控除は、年間10万円以上(または所得の5%以上)の医療費を支払った際に利用できる重要な制度です。対象となる医療費の範囲は思っているより広く、通院交通費や市販薬なども含まれます。
申請にあたっては、領収書の整理・保管を日頃から行い、e-Taxやスマホを活用することで効率的に手続きを進められます。特に家族分をまとめて申請する場合は、所得の高い人が申請することで節税効果を最大化できます。
今年から医療費の記録をしっかりと管理して、来年の確定申告で医療費控除を活用しましょう。わからないことがあれば、税務署の相談窓口や確定申告書等作成コーナーのヘルプ機能も活用できます。


