なぜ確定申告でミスをしてしまうのか?

初めての確定申告で「書類の書き方がわからない」「期限に間に合わない」「計算が合わない」といった悩みを抱えていませんか?
確定申告は一年に一度しか行わないため、慣れないのは当然です。しかし、よくあるミスのパターンを知っておけば、多くのトラブルは回避できます。
この記事では、初心者が陥りがちな10の代表的なミスとその回避策を詳しく解説します。事前に対策を知ることで、安心して確定申告を進められるでしょう。
確定申告の基本をおさらい

まず、確定申告の基本的な仕組みを確認しましょう。
確定申告とは、前年1月1日から12月31日までの所得を計算し、納める税額を確定させる手続きです。会社員でも副業収入が20万円を超える場合や、医療費控除を受ける場合は申告が必要になります。
申告期間と対象者
- 確定申告 いつまで:翌年2月16日〜3月15日
- 確定申告 いつから:2月16日から受付開始
- 個人事業主、副業収入がある会社員、年金受給者などが対象
申告方法は主に3つあります:
- 確定申告書等作成コーナー:国税庁のWebサイトで作成
- 確定申告 スマホ:スマートフォン専用サイトで簡単申告
- 税務署への直接提出:紙の申告書を持参または郵送
近年はスマホでの申告が普及し、初心者でも比較的簡単に手続きできるようになりました。ただし、基本的な知識がないとミスを犯しやすいのも事実です。
「確定申告は難しい」というイメージがありますが、正しい手順と必要書類を準備すれば、意外とスムーズに進められます。
初心者がやりがちミス10選と回避策

ミス1:申告期限を勘違いしている
結論:確定申告の期限は毎年3月15日までですが、多くの初心者が「3月31日まで」と勘違いしています。
なぜ起きるか:年度末の3月31日と混同してしまうため。また、還付申告は1月から受け付けているため、時期を誤解することも。
具体例:「まだ3月だから大丈夫」と思っていたら、実は期限まで数日しかなかったケース。
回避策:確定申告の期限は2月16日〜3月15日と覚える。カレンダーにマークして、2月中旬には準備を始めましょう。
ミス2:必要書類を揃え忘れる
結論:源泉徴収票や各種控除証明書など、必要書類の準備不足で申告が遅れるケースが頻発します。
なぜ起きるか:どの書類が必要か把握していない、または紛失してしまうため。
具体例:医療費控除を受けたいのに領収書を捨ててしまった、生命保険料控除証明書が見つからないなど。
回避策:
- 年明けから必要書類リストを作成
- 源泉徴収票、保険料控除証明書、医療費領収書などを専用ファイルで保管
- 確定申告 必要書類を事前にチェックリスト化
ミス3:控除の申請漏れ
結論:適用できる控除を知らずに申告し、余分な税金を払ってしまうミスです。
なぜ起きるか:控除制度の種類や適用条件を理解していないため。
具体例:医療費が10万円を超えているのに医療費控除を申請しない、ふるさと納税をしたのに寄附金控除を忘れるなど。
回避策:主要な控除項目(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除など)を事前に確認し、該当するものがないかチェックしましょう。
ミス4:医療費控除の計算ミス
結論:医療費控除は「支払った医療費から10万円(または総所得の5%)を差し引いた金額」ですが、計算を間違える人が多数います。
なぜ起きるか:医療費の合計額がそのまま控除額だと思い込んでいるため。
具体例:年間15万円の医療費を支払ったのに、15万円全額が控除されると思っている(実際は5万円の控除)。
回避策:医療費控除額 = 支払医療費 − 10万円の公式を覚え、正確に計算しましょう。
ミス5:経費の計上間違い
結論:個人事業主や副業の場合、プライベートと事業の経費を混同してしまうミスが発生します。
なぜ起きるか:経費として認められる範囲を正しく理解していないため。
具体例:自宅の家賃全額を経費にする、プライベートな飲食費を交際費として計上するなど。
回避策:事業に直接関係する支出のみを経費として計上し、家事按分が必要なものは適切な割合で分けましょう。
ミス6:青色申告と白色申告の選択ミス
結論:青色申告の届出を提出していないのに青色申告しようとしたり、逆に青色申告のメリットを知らずに白色申告を選んでしまうミスです。
なぜ起きるか:事前の届出が必要であることや、それぞれのメリット・デメリットを理解していないため。
具体例:青色申告特別控除65万円を受けられるのに白色申告を選択してしまう。
回避策:青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内に提出する必要があります。事業所得がある場合は青色申告を検討しましょう。
ミス7:マイナンバーの記入漏れ
結論:確定申告書にマイナンバーの記入や本人確認書類の添付を忘れるミスが多発しています。
なぜ起きるか:マイナンバー制度に慣れていない、記入欄を見落としてしまうため。
具体例:申告書を提出したが、マイナンバー未記入で税務署から連絡が来るケース。
回避策:申告書提出前にマイナンバー記入欄と本人確認書類の準備を必ずチェックしましょう。
ミス8:銀行口座情報の誤記入
結論:還付金を受け取る口座の情報を間違えて記入し、還付が遅れるミスです。
なぜ起きるか:口座番号や金融機関コードを記憶で書いてしまい、確認を怠るため。
具体例:口座番号を1桁間違えて記入し、還付金が振り込まれないケース。
回避策:通帳やキャッシュカードを見ながら正確に記入し、記入後に再度確認しましょう。
ミス9:提出方法の選択ミス
結論:e-Taxを使おうとしたが設定が複雑で断念したり、郵送で提出したが消印日を間違えるミスです。
なぜ起きるか:各提出方法の特徴や注意点を理解せずに選択してしまうため。
具体例:スマホ申告を試したが対応していない項目があり、結局紙で提出し直すことになった。
回避策:自分の申告内容に適した方法を事前に確認し、確定申告 スマホ対応範囲を把握してから選択しましょう。
ミス10:修正申告の方法を知らない
結論:申告後に間違いに気づいたが、修正申告や更正の請求の方法がわからず放置してしまうミスです。
なぜ起きるか:修正手続きの存在や方法を知らないため。
具体例:控除の申請漏れに後から気づいたが、修正できることを知らずに諦めてしまう。
回避策:税額が増える場合は修正申告、減る場合は更正の請求という制度があることを覚えておき、間違いに気づいたら速やかに手続きしましょう。
確定申告をスムーズに進めるコツ
これまで紹介したミスを防ぐためには、事前準備が何より重要です。以下のコツを活用して、スムーズな申告を目指しましょう。
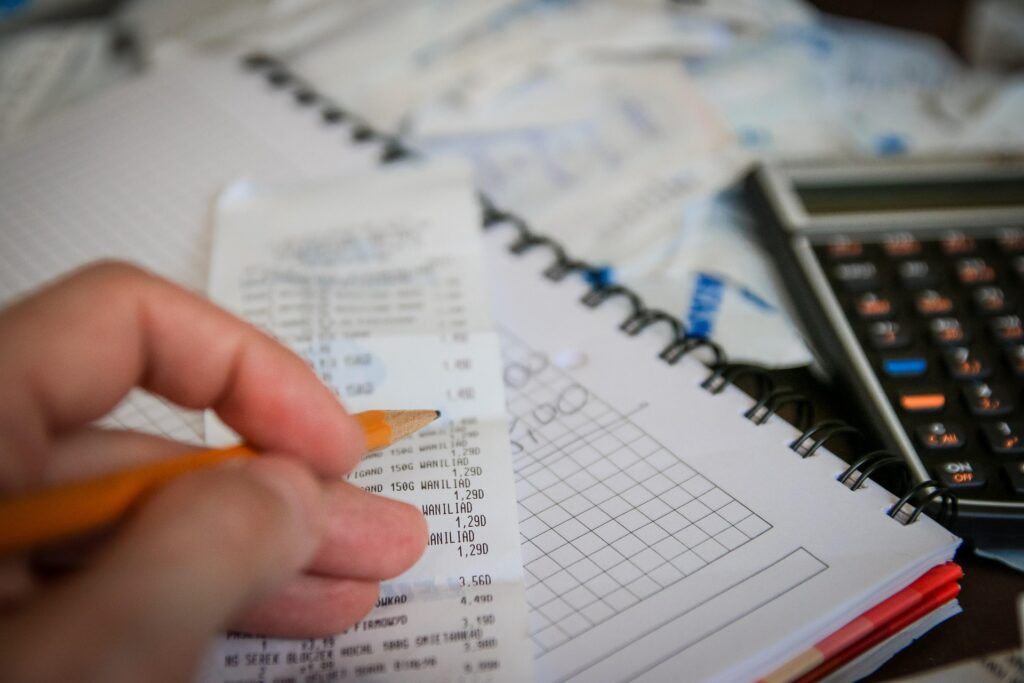
「準備8割、作業2割」の心構えで取り組むことが、確定申告成功の秘訣です。
事前準備の徹底
年明けから以下の準備を始めましょう:
- 必要書類のチェックリスト作成
- 前年の申告書控えの確認
- 収入・支出の整理
- 適用可能な控除の洗い出し
スマホ申告の活用
確定申告 スマホでの申告は年々機能が向上しており、給与所得者の医療費控除やふるさと納税などは簡単に処理できます。ただし、事業所得がある場合は機能制限があるため、事前に対応範囲を確認しましょう。
確定申告書等作成コーナーの効果的な使い方
国税庁の確定申告書等作成コーナーは無料で利用でき、計算も自動で行われます:
- 入力ガイダンスに従って順番に進める
- 不明な点は「?」マークのヘルプを活用
- 途中保存機能を使って複数回に分けて作業
プロに相談するタイミング
以下の場合は税理士などの専門家への相談を検討しましょう:
- 事業所得が複雑で計算に不安がある
- 不動産所得や株式譲渡がある
- 相続や贈与に関する申告が必要
- 税務調査の対象になった
時間コストを考えると、複雑なケースでは専門家に依頼する方が結果的に効率的です。
まとめ:ミスを防いで正しく申告しよう

確定申告での主なミスは以下の10点でした:
- 申告期限の勘違い
- 必要書類の準備不足
- 控除の申請漏れ
- 医療費控除の計算ミス
- 経費計上の間違い
- 青色・白色申告の選択ミス
- マイナンバー記入漏れ
- 口座情報の誤記入
- 提出方法の選択ミス
- 修正申告方法の無知
これらのミスは事前の準備と正しい知識があれば十分に防げます。特に重要なのは、申告期限の正確な把握と必要書類の早期準備です。
今すぐ取るべき行動:
- カレンダーに確定申告期限(3月15日)をマーク
- 必要書類のチェックリスト作成
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスして操作方法を確認
初めての確定申告は不安かもしれませんが、正しい準備と手順を踏めば必ず完了できます。この記事を参考に、安心して確定申告に取り組んでください。


