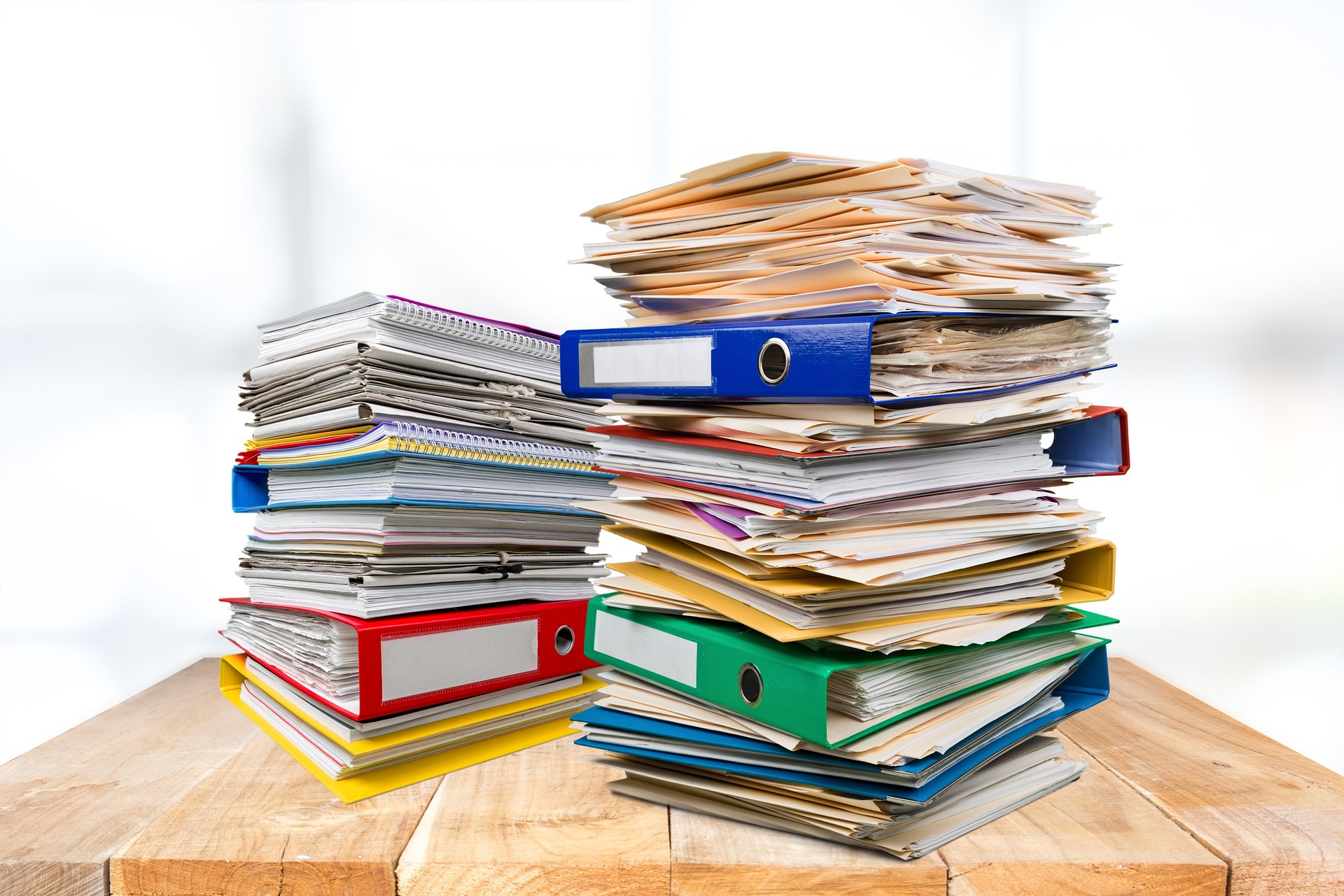毎年の確定申告、添付書類で迷っていませんか?

「今年の確定申告で提出する書類は何が必要?」「去年まで添付していた書類が今年は不要って本当?」そんな疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
実は、2020年以降の税制改正により、多くの添付書類が提出不要になりました。しかし、この変更について正確に理解している人は意外と少ないのが現状です。
この記事では、添付が不要になった書類の具体的なリストから、e-Taxやスマホでの申告メリット、そして重要な保管義務まで、初心者の方でも分かりやすく解説します。正しい知識を身につけて、今年の確定申告をスムーズに進めましょう。
添付不要になった書類とは?基本解説

2020年(令和2年)分の確定申告から、多くの添付書類の提出が不要になりました。これは国税庁による手続きの簡素化・デジタル化推進の一環として実施された重要な改正です。
従来の確定申告では、所得控除や税額控除を受けるために、証明書類の原本やコピーを申告書と一緒に提出する必要がありました。しかし、この改正により、申告書への記載のみで控除が適用されるようになったのです。
ただし、重要な点として、「提出不要」と「保管不要」は全く異なるということを理解しておく必要があります。
添付書類の提出は不要になりましたが、税務調査の際には提示を求められることがあるため、5年間(青色申告の場合は7年間)の保管義務は継続しています。
この変更により、郵送での申告時の書類準備が大幅に簡素化され、e-Taxを利用したデジタル申告もより便利になりました。特に、スマホからの申告では、書類をスキャンしたり撮影したりする手間が省けるため、申告のハードルが大きく下がっています。
また、申告期限である3月15日までの申告がより効率的に行えるようになり、多くの納税者にとって負担軽減につながっています。
添付が不要になった主な書類一覧
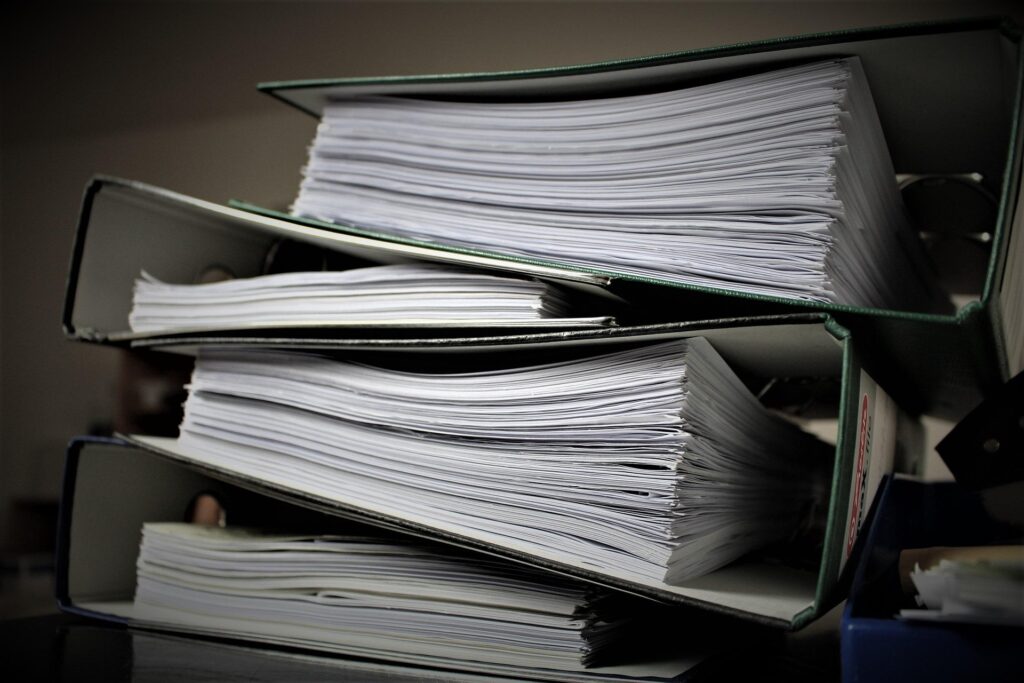
給与所得・年金関係の書類
給与所得者や年金受給者の方が最も頻繁に扱う書類群です。以下の書類について、提出は不要ですが必ず保管してください。
- 給与所得の源泉徴収票:勤務先から受け取る最も重要な書類
- 退職所得の源泉徴収票:退職金を受け取った場合
- 公的年金等の源泉徴収票:国民年金、厚生年金等
- 年末調整で控除を受けた各種証明書:すでに年末調整済みのもの
これらの書類は、申告書の該当欄に金額や内容を正確に記載するだけで控除が適用されます。記載内容に間違いがないよう、原本を確認しながら慎重に入力することが重要です。
医療費控除関係の書類
医療費控除は多くの方が利用する控除ですが、2017年分から既に簡素化が進んでいました。現在は以下の取り扱いとなっています。
- 医療費の領収書:提出不要(5年間保管必須)
- 医療費控除の明細書:申告書に添付または入力必要
- 医療費通知(医療費のお知らせ):利用する場合の原本保管
- セルフメディケーション税制の証明書類:提出不要(保管必須)
医療費控除を適用する際は、医療費控除の明細書への記載が必要です。e-Taxやスマホでの申告では、この明細を画面上で入力するだけで済むため、非常に便利です。
保険料控除関係の書類
生命保険や地震保険などの控除証明書も添付不要となっています。
- 生命保険料控除証明書:一般・介護医療・個人年金
- 地震保険料控除証明書:地震保険・旧長期損害保険
- 社会保険料控除証明書:国民年金保険料等
- 小規模企業共済等掛金控除証明書:iDeCo等
年末調整で控除を受けていない場合や、年末調整後に新たに判明した控除がある場合は、確定申告で正しく申告する必要があります。証明書の保管を忘れずに行いましょう。
寄附金控除(ふるさと納税)の書類
ふるさと納税の寄附金受領証明書も添付不要になっています。ただし、ワンストップ特例制度を利用していない場合の取り扱いに注意が必要です。
- 寄附金受領証明書:ふるさと納税の証明書
- 寄附金控除に関する証明書:認定NPO法人等への寄附
- 政治活動に関する寄附金の証明書:政治献金等
ふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例制度の利用有無を必ず確認してください。6団体以上への寄附や、他の控除で確定申告が必要な場合は、必ず寄附金控除として申告が必要です。
e-Taxならさらに簡単!スマホ申告のメリット

e-Taxを利用することで、確定申告はさらに効率的になります。特にスマホでの申告は、多くのメリットがあります。
まず、マイナンバーカードを利用したID・パスワード方式により、税務署での事前手続きが不要になりました。スマホのマイナンバーカード読み取り機能を使えば、自宅から24時間いつでも申告が可能です。
2025年分の確定申告から、さらなる機能向上が予定されており、給与所得の源泉徴収票の情報がマイナポータル経由で自動取得できるようになる予定です。これにより、手入力の手間が大幅に削減されます。
- 24時間365日利用可能:申告期限間際でも安心
- 計算ミスの防止:システムが自動計算
- 還付金の早期受け取り:書面申告より2~3週間早い
- 添付書類の電子送信:必要な場合のみPDF等で送信
e-Taxでは、添付が必要な書類があっても、PDF形式での電子送信が可能です。スキャナーやスマホのカメラで書類を読み取り、システム上でアップロードするだけで完了します。
また、過去の申告データを参照できるため、前年と同様の控除を受ける場合の入力が非常に簡単になります。特に個人事業主の方や、毎年同じような控除を受ける方にとって大きなメリットです。
申告期限の3月15日までの期間中は、税務署の窓口が混雑することが予想されますが、スマホでの申告なら待ち時間なく手続きが完了します。
注意点:提出は不要でも保管は必須

最も重要な注意点は、提出不要と保管不要は全く異なるということです。確定申告書への添付は不要になりましたが、法定保管期間中の書類保管義務は継続しています。
保管期間は以下の通りです:
- 白色申告の場合:申告期限から5年間
- 青色申告の場合:申告期限から7年間
- 法定調書等:7年間(所得税法規定)
税務調査が実施された場合、これらの書類の提示を求められることがあります。書類を紛失していた場合、控除の適用が取り消される可能性があり、追加の税額と延滞税が発生するリスクがあります。
国税庁の統計によると、個人の税務調査件数は年間約6万件です。確率は低いものの、調査対象となった際に必要書類を提示できないことによる不利益は避けるべきです。
書類の保管方法としては、原本の保管が基本ですが、デジタル化による保管も認められています。ただし、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるため、詳細は税務署にご相談ください。
紛失のリスクを避けるため、確定申告後は専用のファイルやフォルダで整理保管することをお勧めします。
まとめ・次にやるべきこと

確定申告の添付書類簡素化により、申告手続きは大幅に効率化されました。多くの証明書類は提出不要となりましたが、5年間(青色申告は7年間)の保管義務は継続していることを必ず覚えておきましょう。
e-Taxやスマホでの申告を活用することで、さらに便利で正確な申告が可能になります。申告期限の3月15日までに余裕を持って準備を進めることが重要です。
今すぐ行うべきアクション:
- マイナンバーカードの準備:e-Tax利用のための必須アイテム
- 必要書類の整理:源泉徴収票等の収集と確認
- e-Taxの利用者識別番号取得:初回利用時に必要
- 過去の証明書類の適切な保管:ファイリングの見直し
正しい知識と準備により、今年の確定申告をスムーズに完了させましょう。分からないことがあれば、税務署の相談窓口や国税庁のホームページも活用してください。